一級建築士試験の攻略について。
私見ですがまとめました。
まずは私の経過から。
私が一級建築士試験を初めて受けた時は2020年です。
専門卒なため二級建築士まで2年の設計等の実務経験が要り、
2008年卒ですが2015年に初受験。
学科独学、
製図日建学院短期で、
二級建築士を取りました。
二級として4年の実務経験で一級建築士の受験ができました。
2019年夏頃から、
市販のテキストと総合資格の過去問7年分を使い独学を開始し、
2020年は72点で18点不足の学科落ち。
2021年も独学、
スマホアプリの過去問集を通勤電車で毎日30分、
だいたい片道20問くらい。
副読本系を追加で1万円分くらい買い、
学科85点で87点に2点足らずに不合格。
2022年に日建の独学支援コース(テキスト+ウェブ講義)で92点、
91点が合格点で初製図に、
2か月日建学院に通って製図ランクⅢ。
2023年は日建の長期製図を受講してランクⅢ。
2024年製図角番ですが資金がないため全日本建築士会の長期を、
講師の紹介と交渉で8割の値段で受講して挑みました。
製図の手ごたえは何とも言えないです。
12月25日まで合否は気にしないでいようと思っています。
結果的には学科は独学でも行けると思います。
初受験の2年前から過去問を買っていて、
学科合格した年には過去問10年分×3周しました。
(科目ごとまとめてやると暗記しやすいです。例えば計画だけ5年分一気に解く)
計画は一問1分かからないくらいだったので、
20問で15分×5年で75分くらい。
過去問は法規は変わるためあまり暗記せずにいたので、
意匠設計の仕事をしているくせに19点しかとれなかったです。
計画は過去問10年の正答率9.5割くらいでした。
19点や20点悪くても18点は固いくらいに過去問をしておき、
本試験では計画が難しく足切りが多い受験年に15点取れました。
合格に大きく貢献したのは2年目以降、
構造力学を1問しか解けない所から、
7~8問中5問ほど取れるくらいに勉強しました。
建築の数学(算数 和差乗除)から始め、
構造力学の副読本は5冊くらい買いました。
一級建築士は科目足切りがあるため、
苦手をじっくりと潰していく根気のいる勉強が必要です。
一級建築士試験の解答枝の6割は過去問使いまわし、
2割は過去問の応用、
残りの2割のみ新規枝なため、
過去10年を8~9割取れれば、
合格圏内に行けると見聞きした記憶です。
難しい問題は2枝は確実に解って潰せて二択になる感じ。
製図は今年、
全日本建築士会の講座を受けて思ったのは、
日建学院の方が丁寧。
映像講義は日曜日の通学時に講義時間内で見れて、
要点がまとまっておりわかりやすい。
全日本建築士会も課題解説は授業の後日観れますが、
チャプター無しの2時間半の講義を観るのもしんどいです。
わかる人は観ないでいいし、
わからなかった課題、
エスキスがまとまらない時に観る感じです。
お金に余裕のある人は総合資格か日建学院。
余裕のない方は学科独学の上、
製図一回目は日建短期、
二~三回目は全日本建築士会長期、
副教材にウラ指導の本やマンガで製図の本。
2回目以降の時は日建の受験年度の市販課題集追加。
まだ今年受かっているのかわからないけれど、
私なりに分析すると学科独学の上、
製図は通学が一番だと思います。
製図は選択肢が多いので迷うと思います。
通信講座でコストを削るか、
通学講座大手でガッツリ向き合うか。
総合資格学院
日建学院
TAC
全日本建築士会
合格ロケット
ウラ指導
スタディング

他にもあると思いますが、
私が知っているだけでもこれだけ選択肢がある。
よく考えて計画的に選んでください。
最後におすすめの本をいくつか挙げておきますので、
ぜひ買って勉強に役立ててください。
それでは、また。
新品価格 |  |
新品価格 |  |
新品価格 |  |
新品価格 |  |
新品価格 |  |
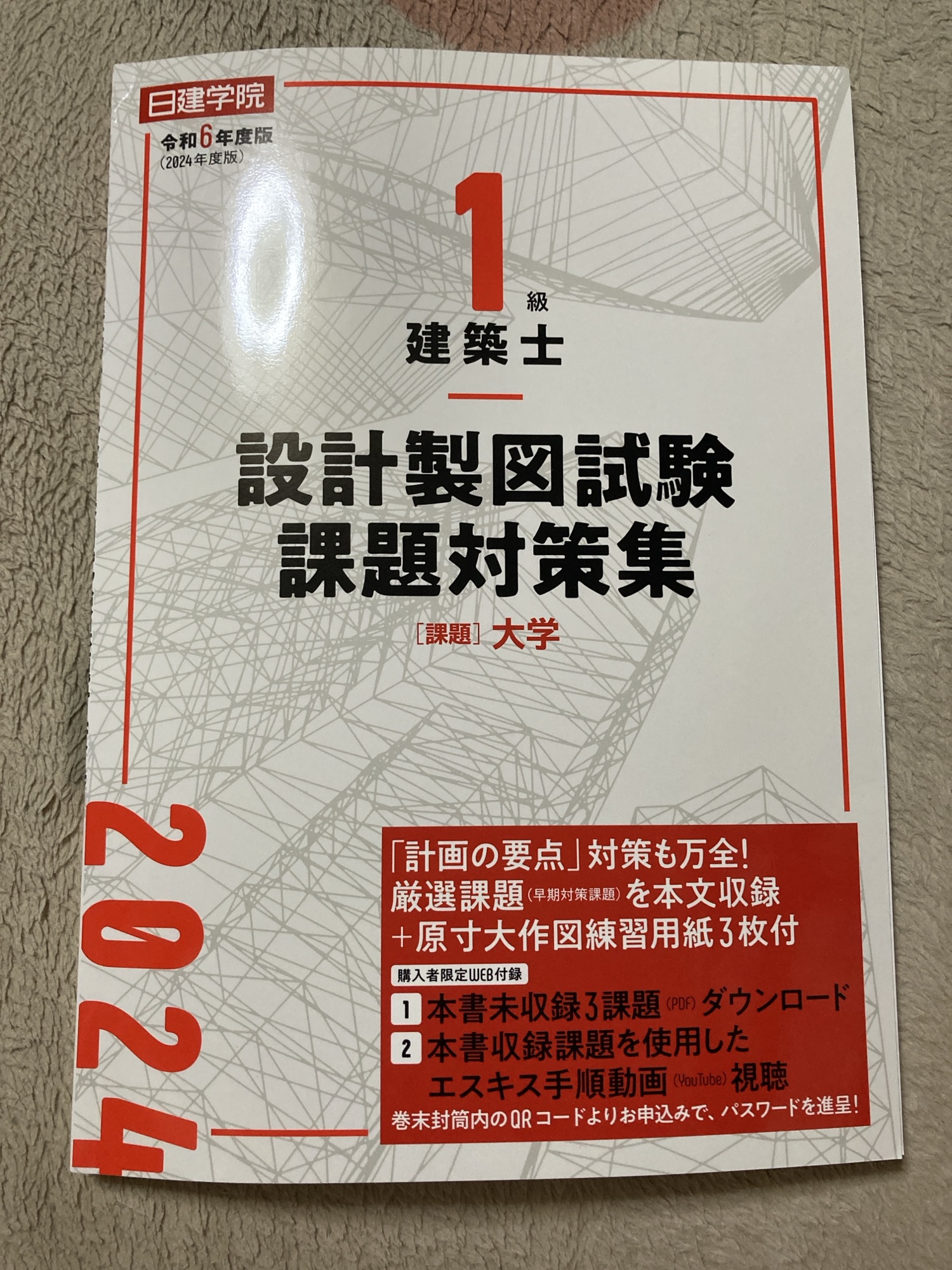
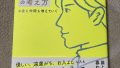

コメント