次の日曜日
7月28日が今年の一級建築士学科試験の日です。
昨年の製図試験に向けた日建学院の長期講座で、
隣の席だったMさんは、
去年が角番でした。
彼は残念ながらランクⅣで不合格だったのですが、
製図試験直後から、
今年の学科試験に向けた勉強を開始したらしいです。
長い間試験のために使ってきた時間と労力が、
報われる時が来るとしたら、
それは合格をしたときでしょうね。
受かると良いな。
建築を仕事にする時に、
一級建築士資格は欲しいです。
私は2008年の専門学校卒で、
フリーターやら病気やらと紆余曲折で、
二級建築士資格を取得するのが2016年と遅かったため、
一級建築士試験の受験資格を得るのに、
2020年までかかった。
学科試験を2回落ち、
製図試験も2回落ちたので、
今年の製図試験が角番の、
一級受験5回目です。
今度の金曜に今年の製図課題が発表されるので、
来週から試験までの2か月半ほど、
10月13日までは忙しくなりそうです。
二級建築士の受験者は、
課題も発表されていて、
学科試験合格見込みの人は、
すでに9月15日の製図試験に向けた勉強をしているでしょうね。
私も2015年の春から夏は、
二級建築士試験に向けた日々でした。
頑張ったという自負のある思い出です。
20代を紆余曲折だったけれど、
30手前の二級建築士を取ってからは、
真っ直ぐに建築の道を生きています。
2015年の試験で二級を取れて良かった。
建築の道を行くときに、
いつかは一級建築士資格は欲しいけれど、
キャリアのことも考えて二級建築士から受験するのもおすすめです。
数年前の改正で建築系学科の大卒者は、
いきなり一級を受験できるようになった。
実務経験は登録要件であとからでも良いとなったため、
二級を受けずに一級から受験する人も多いでしょうね。
私は大卒者でもまずは二級建築士を受験することをお勧めします。
理由は二つあって、
第一に登録まで2年の実務経験を要する一級より、
まず二級を取ることで、
管理建築士の資格要件を早く満たせるからです。
第二に一級建築士の試験の高い難易度から、
二級建築士の方が勝ち目が大きいことです。
無いよりは二級でも資格を持っていることで、
転職や就職に有利になります。
二級建築士は私の場合、
フリーターの時に受けたので、
4月の受験申し込み後から、
バイトのシフトを減らし週に2日にして、
バイト以外の日を一日8時間くらい勉強しました。
独学で700時間くらい勉強した計算になりますが、
それで合格できました。
製図は独学は厳しそうだからと、
日建学院の短期講座を受けました。
シフトを週に2日になんて出来る人なら良いけれど、
そうは出来ない人がほとんどでしょうね。
それならば、短期集中ではなく、
長期間毎日1時間とかでも継続していくことで、
きっと二級建築士に受かると思います。
独学で受けるメリットの一つは、
費用が抑えられること。
デメリットは情報を自ら集め選択する必要があること。
独学を支援するサービスもあるので、
資格予備校含め、
自分に合うものを検討してみてください。
スキマ時間などの勉強なら、
スマホを使った勉強がおススメです。
私が一級建築士の学科独学での合格の一因は、
TKofficeという所のスマホ過去問アプリを、
通勤電車で毎日15分×行き帰り勉強した事もあると思います。
自分がすでに学んだところ、
間違えて答えたところなどが、
可視化できることがスマホ勉強の良い所です。
私は使わなかったけれど、
通信教育も今はスマホ勉強を支援してくれます。
スタディングは料金も安いので始めやすいしお勧めします。

以下はスタディングのサイトより。
◆スタディングの強み
・【時間がなくてもOK】スマホ・PC・タブレットで学べるため、日々忙しく勉強時間の取りづらい
社会人・主婦・学生などの方に向いています。低価格で経済的負担も少ないです。
・【見やすく分かりやすい】授業風景を録画しただけなのではなく、映像講座として
専用のフォーマットで編集された講座は、視覚的で理解しやすいと好評です。
・【暗記力に自信がなくてもOK】脳科学に基づき暗記を補助する便利なツールや、記憶が消えないうちに
定着を促進する問題練習機能も充実しており、無理なく進めて合格できる実力がつきます。
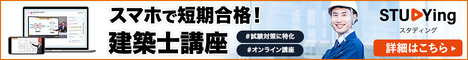
もちろん一級建築士も学科試験を独学で受かることは、
私にもできたのできっと可能です。
来年の試験に向けて頑張る人はぜひ↑のバナーリンクからどうぞ。
今年の製図試験こそは合格し、
一級建築士資格が欲しいです。
合格目指して頑張りましょう。
それでは、また。
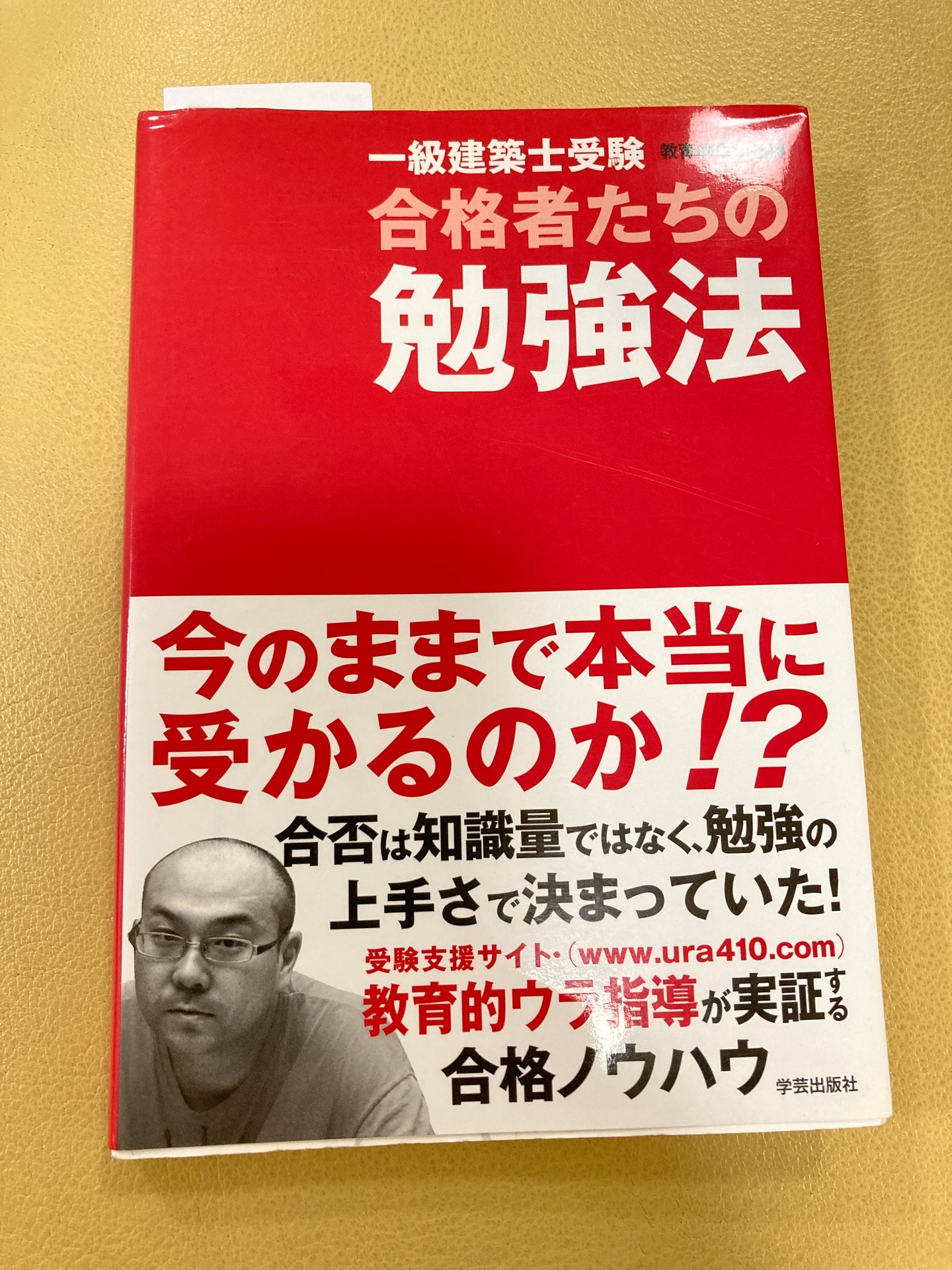

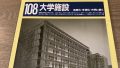
コメント